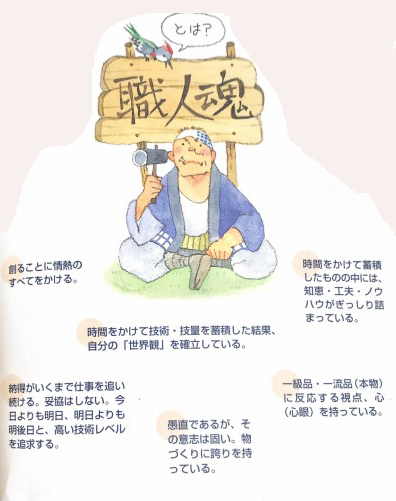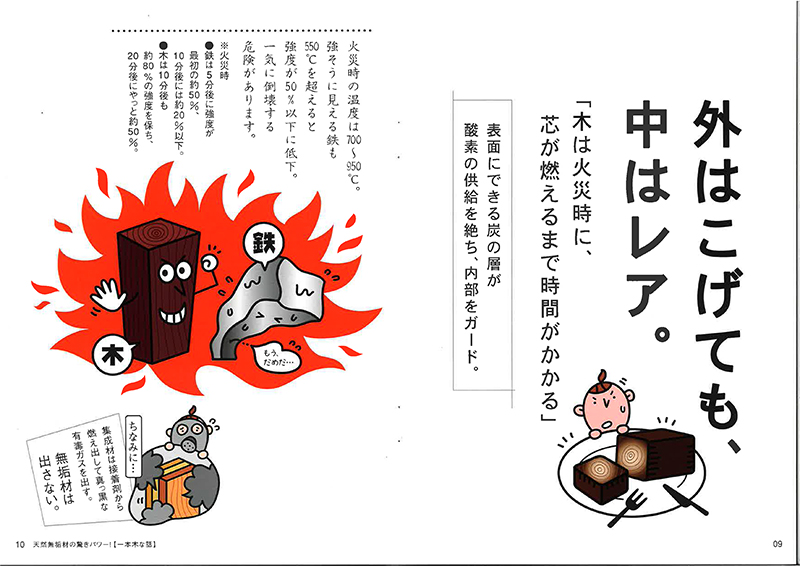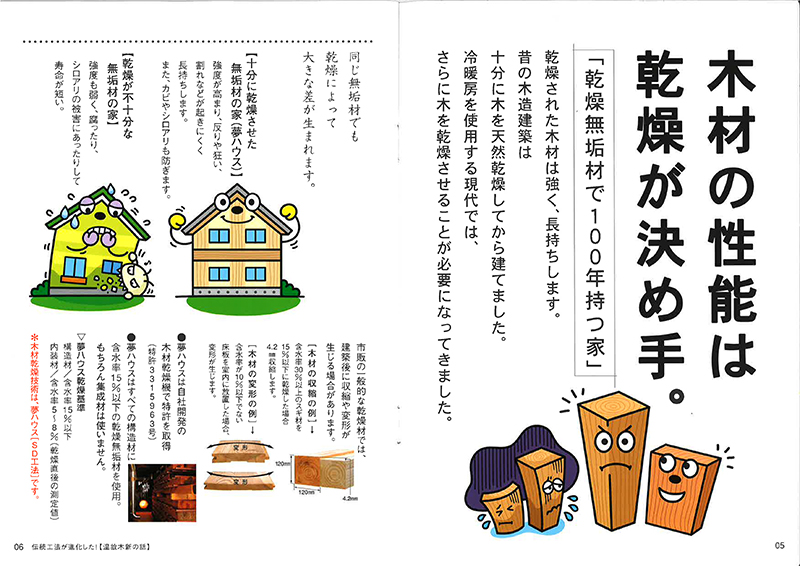最近は、北欧や北米のように、気密性・断熱性を高め、
温度を一定に保つことで快適な室内環境を求める住宅が
多くなりました。一般的に高気密・高断熱と言われる
住宅は、外断熱を採用し、窓にはアルミサッシ、ペアガラス
などを用います。外断熱とは、住まい全体を構造体の外側から、
断熱材ですっぽりと覆ってしまう方法です。高気密・高断熱の
住宅には、冷暖房効率を高め、ランニングコストを抑えるという
目的もあります。
ところが、高気密の仕様では、新鮮な外気が入りにくく、
内部には汚れた空気が停渋しがちでした。さらに湿度の高い
日本では結露が発生し、カビの問題、構造体の傷みの問題など
がクローズアップされるようになりました。
日本の住まいづくりにおいては、湿潤な気候を考慮に入れて、
住まいが十分に“呼吸”できる工法、断熱仕様を追求することが
大切です。住まいと住まう人の健康を考えた、本当の意味での
快適性を実現させることが重要なポイントとなります。