まにゃまる日記
2024.7.2
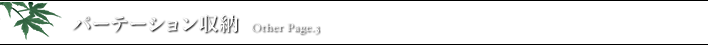


(A)桐製のスライド収納。
納める量に応じて、伸縮させれば、収納力アップ。
洋服掛け収納ラックと組み合わせれば、お部屋のアレンジも自由自在。
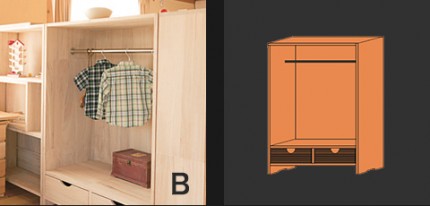
(B)毎日着る服や道具を収納。
子供部屋の間仕切りとしても活用でき、桐で作られているため軽くて移動も楽にできます。

2024.6.29
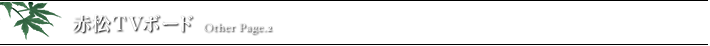

下部引き出しが自在に可動。
長さを伸ばしたり縮めたり、お部屋に合わせてアレンジできます。



2024.6.27
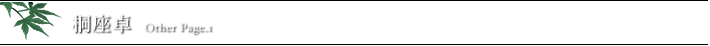

天然の桐の原板を段違いに2枚組み合わせることで、
単調な座卓に動きを与えます。
とても軽い桐座卓は、女性でも簡単に移動させることができます。



2024.6.25
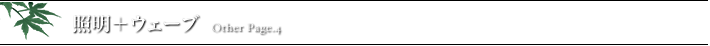
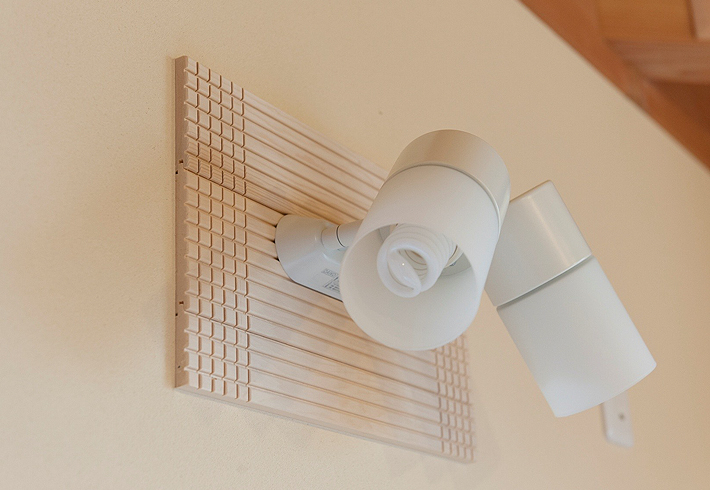
味気なくなりがちな照明器具まわりも、ウェーブタイルなどをバックボードにしてアレンジすれば、
全く違った雰囲気を出してくれます。



2024.6.22
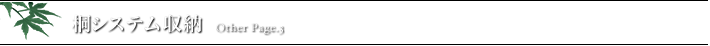

桐システム収納をアレンジして施工すると、
総桐のウォークインクローゼットが完成。
調湿、防カビ、防虫に優れた素材は、
衣類や布団を守ります。




























