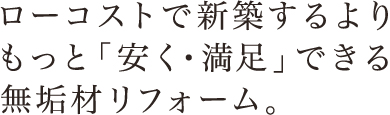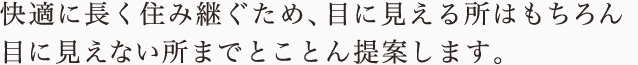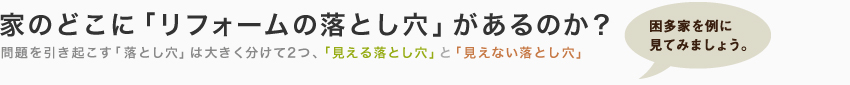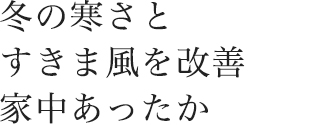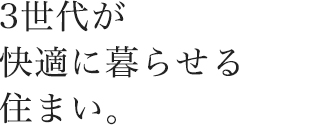まにゃまる日記

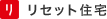
H様邸
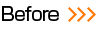


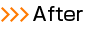

H様の家づくりエピソード
築40年の旧宅は、たくさんの部屋で細かく区切られていて無駄が多く、
滅多に使わない和室は大きなデッドスペースになっていました。
さらに、冬は断熱性の低さとすきま風に長年悩まされ続けていました。
愛着のある我が家で長く快適に暮らすため、全面リフォームをすることにしました。
リフォーム後の我が家は明るく開放的な空間に生まれ変わり、
断熱性能が格段に上がったため薪ストーブ1台で家中が暖まります。
「よくここまで変わったな」と驚いています。
他社さんとも相見積もりを取りましたが、結果的に標準仕様の質が高い分、
夢ハウスが一番納得できる価格でした。
正直、もっと値が張るイメージだったので嬉しい誤算でした。






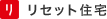
T様邸
T様の家づくりエピソード
16年前に一度水回りと2階のリフォームをしたのですが、
間取りの悪さや不便さ・寒さ・暗さは相変わらずで、
改めて全面リフォームを考えるようになりました。
部屋数は多かったのですが、大勢で集まれる広い空間がなく
物置と化した和室がいくつもありました。
夢ハウスに決めたのは、モデルハウスに宿泊体験をしたとき。
その暖かさと開放的な広さや明るさに感動したんです。
リフォーム後の間取りは、1階に親戚一同も集まれる広いLDKと和室、
2階には若世帯のミニキッチン付きのセカンドリビングがあり、
玄関横におばあちゃんの洋室を設けてもらいました。
それぞれのプライベート空間に加えて十分な収納スペースもあり、
家族全員がとても気に入っています。
4世代・6人家族の私たちの要望を見事に叶えていただきました。
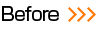


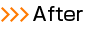









 限定でトマト直売しています
限定でトマト直売しています







 限定でトマト直売しています
限定でトマト直売しています