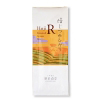旧池新田村(現御前崎市)出身で政治家、実業家として活躍した丸尾文六(1832~96年)
1871年(明治4年)に牧之原台地の茶園開墾を始めて今年は150周年に当たります。
丸尾は当時の静岡藩の依頼で、大井川への渡し船の設置で職を失った川越人足を雇って開墾に着手しました。
重労働に耐えかねて約半数が去ったが、丸尾は残った人足で茶園を切り開き、73年に初めて摘採、製茶に成功。
79年には横浜で開かれた全国規模の茶の品評会で「一等」に輝き、その後も博覧会などで受賞を重ねて名声を得ました。
物産会社や汽船会社も設立し、茶の海外輸出にも尽力しました。