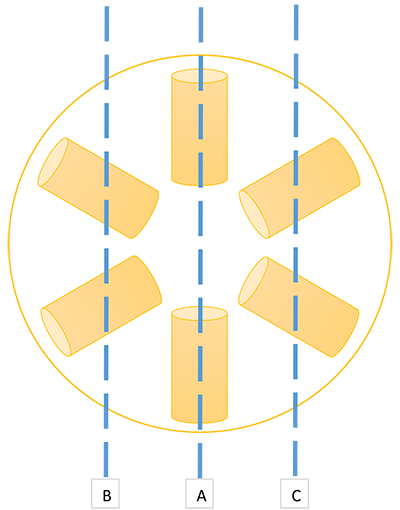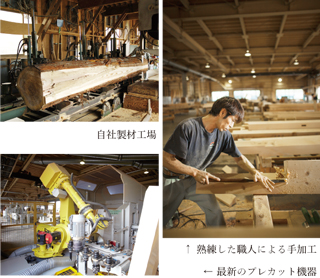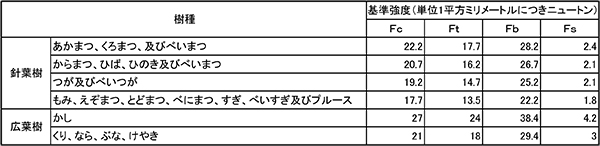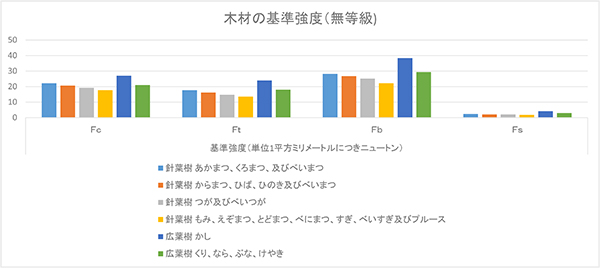芯が入り、大きな流れ節となって出ていきます。
生き節の場合はまだ見た目の話ですが、死節になっていると乾燥材に節がめくれてしまったり、
削った際に節が飛んでいきます。
また、芯が残っていることにより、乾燥によるねじれも起こりやすいのです。
なぜ流れ節が出るのでしょうか?
丸太の大きさが不十分だと、どうしても芯を通る製材の割り方となります。
Aの場合は、枝と挽目が平行になってしまいます。
この場合に、材表面に流れ節として出てきます。
B・Cの位置であれば、枝に対して垂直に切るので枝を輪切りにする形になり、
通常の丸い節になります。
この様に、大径木で流れ節を出さないように製材することは非常に難しく、
大きな丸太を必要とします。